どうも、じゅじゅいちです。
東村山市にある国立ハンセン病資料館に行ってきました。ハンセン病の知識普及に関わってきた藤楓協会の40周年を機に1993年に高松宮記念ハンセン病資料館として開館。高松宮宣仁親王殿下(大正天皇の第三皇子)は藤楓協会の総裁を務めていました 。リニューアルを経て2007年に国立ハンセン病資料館として再開館しました。

秋津駅や新秋津駅から徒歩20分程度ですかね。入館無料です。
ハンセン病は「らい菌」に感染することで起こる病気で、感染力が弱くうつりにくい病気です。たとえ感染しても現代においては発症することはほぼないそうです。日本人の新規患者数は2015年と2017年に1人、2016年には0人です。また早期に発見し治療を行えば後遺症も残らないとのことです。
受付入ってすぐのところには新聞の展示がありました。2001年にハンセン病の国の責任を問う裁判で原告勝訴の判決が出て、当時の小泉総理が控訴を断念したという記事がありました。
映写機や消防団団服、ホース車の展示もありました。隔離施設なので映画は貴重な娯楽だったとか。感染を恐れて消防署が来てくれないため入所者で消防団を結成しなくてはならなかったそうです。
2Fの展示は3つの部屋に分かれています。展示室1は歴史展示です。1907年に各地を放浪するらい病患者を収容する法律「癩予防ニ関スル件」が制定され隔離が始まりました。そして1931年に癩予防法が成立し、全てのらい病患者の強制隔離がすすめられました。1930年代からは無癩県運動という県内から癩をなくそうという運動も始まったということです。1953年に制定された「らい予防法」においても引き続き隔離政策がとられました。1996年にようやく「らい予防法」が廃止されました。
展示室2は癩療養所についての展示です。癩病がいかに辛く苦しいかということがよくわかります。また入所者同士の結婚は許されていましたが、子供を作ることは許されず断種や中絶などが行われていたようです。展示室3は「生き抜いてきた証」というテーマです。創作活動や回復者による証言コーナーなどがあります。さらに企画展示室にはハンセン病療養所の入所者が描いた絵画の展示もありました。
現在ハンセン病療養所は国立が13ヵ所、私立が1ヵ所あります。ここ国立ハンセン病資料館は多磨全生園(たまぜんしょうえん)という療養所の敷地内にあります。2019年5月1日現在入所者は全国に1215名いて、ここ多磨全生園には156名が暮らしているとのことです。

国立ハンセン病資料館のある多磨全生園も見ていきます。1909年、公立療養所全生(ぜんせい)病院として設立されました。

尊厳回復の碑。入所者は子供を作ることは認められておらず、妊娠したら堕胎されられました。当時は感染経路が分かっていなかったため将来明らかにすることができるかも知れないと考えた科学者が胎児をホルマリン漬けにしたらしいです。それを供養するために作られたのがこの碑だそうです。

納骨堂です。療養所に収容されると二度と戻ることができず、ふるさとに骨を埋めることもできなかったそうです。そこで1935年に納骨堂を建立したとのことです。納骨堂が劣化してきたので1985年に入所者の寄付によって再建し3493名の遺骨を納めたとのこと。

日蓮正宗蓮華堂。宗教地区と呼ばれるこのエリアには様々な宗派のお寺、教会があります。

真宗会館和光堂。

真言宗智山派全生大師堂。白い線が引かれていますがこれは目の不自由な人のものだそうです。白は多少目が不自由になっても知覚できるそうです。

日蓮宗会堂。

カトリック教会。仏教だけでなくキリスト教もあるんですね。

秋津教会。プロテスタント。

日本聖公会東京教区聖フランシス聖エリザベツ礼拝堂。キリスト教はカトリックとプロテスタントに大別されますが、聖公会は明確には分類できなさそうです。

宗教地区から離れていますが永代(ながよ)神社があります。天照大神宮、豊受大神宮、明治神宮を祀っているとのこと。本殿や境内の工事は入所者によって行われ、内務省神社局によって永代神社と命名されたとか。
この他、病棟や郵便局などもありました。

多磨全生園の周りは木で囲まれ外から園内が見えないようになっています。他の施設では高い壁で囲まれていたところもあるようです。
先月の6月28日に、熊本地裁でハンセン病隔離政策によって家族にも差別などの被害が及んだということで国の責任を認める判決が出ました。2001年の判決では患者のみでしたが、今回は家族にも被害が及んだことが認められました。7月9日安倍総理は国の責任を認め控訴しないことを表明しました。
かつて不治の病として苦しんだハンセン病のことや、強制的に隔離され人権を無視された人々の生活などがわかる資料館となっていますので皆様も足を運んでみてはいかがでしょうか。

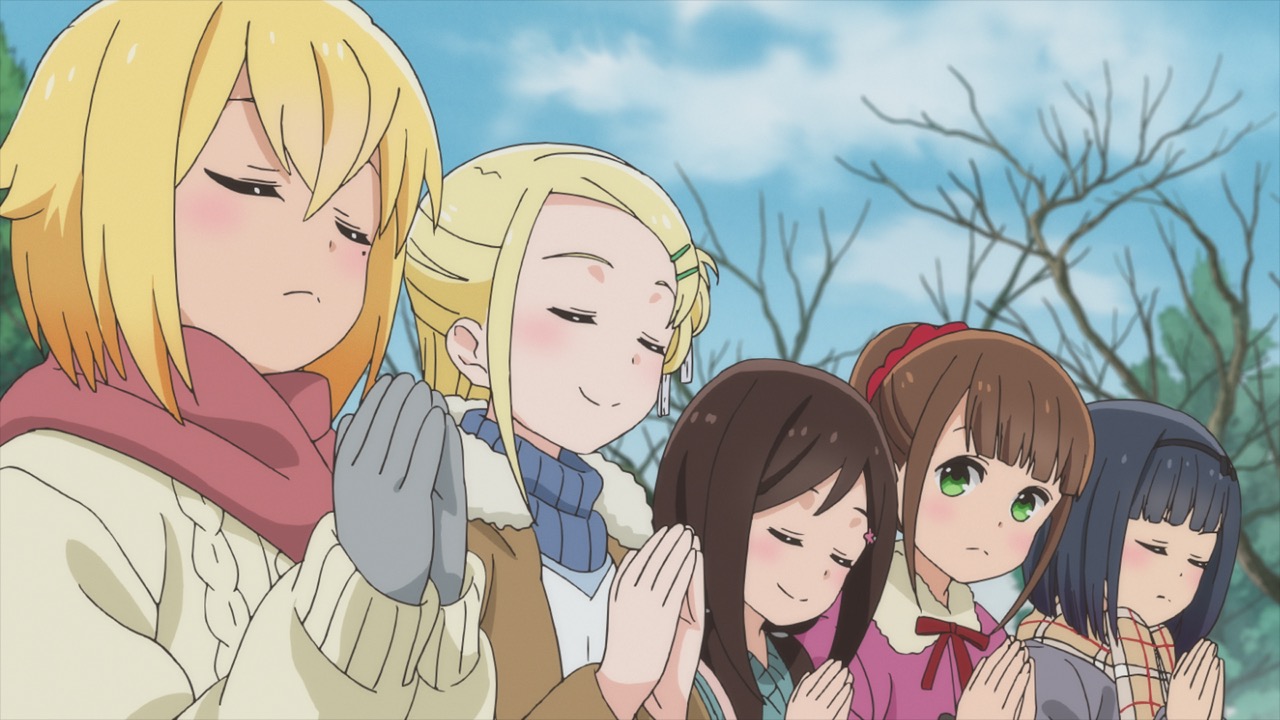

コメント